生き物の命には限りがあり、カブトムシやクワガタにも同様に寿命があります。
昆虫図鑑などで既に常識的に伝えられていることになりますが、ここでは私の飼育体験を基にそれぞれの寿命について触れておきたいと思います。
カブトムシの寿命は?
日本のカブトムシは、一般的には夏に成虫となり地中から地上に現れその夏を終えると寿命を迎えます。
つまり、越冬することなく僅かな期間を持って終わりを迎えるのです。
季節を感じさせる生き物の代表格となっているカブトムシですが、意外に短命なのです。
因みに、昔僕が飼育していたカブトムシで1匹のメスが12月下旬まで生きたことがありました。
確か、電気ストーブ横にケースを置いていたので十分に温かい環境で飼育したことが要因の1つかと思っています。
さて、そんなカブトムシですが、成虫として生きられる夏の期間に繁殖に向けオスとメスは盛んに交尾を行い産卵します。
短命の一因として挙げられるのは運動量の多さです。
特にカブトムシはよく羽根を広げて飛びます。
さらに盛んな繁殖活動にも起因するという見方があります。繁殖には非常にエネルギーを使うということなのでしょう。
クワガタの寿命は?
一方クワガタですが、クワガタは以下のように種類によってその寿命に違いがあります。
・オオクワガタ(3〜4年)※最長7年という例もあります
・ヒラタクワガタ(1〜3年)
・コクワガタ(1〜2年)
・スジクワガタ(1〜2年)
・アカアシクワガタ(1〜2年)
・ネブトクワガタ(1〜2年)
・マメクワガタ(1〜2年)
ほか
・ミヤマクワガタ
・ノコギリクワガタ
ほか
なぜ、クワガタでも種類によって寿命が違うのか?
圧倒的に長寿とされるオオクワガタと短命であるミヤマクワガタ、ノコギリクワガタとの決定的な違いですが、やはり運動量ではないかと思います。
オオクワガタは比較的大人しく、行動範囲が狭いことはあまりにも有名で捕獲が難しい所以であります。
一方ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタについては飼育して思うことは、とにかく動き、そして飛びます。
やはり運動量が多いと消費エネルギーが大きくなり、寿命に直結しているのでは?と仮説ですが思っています。
しかし、これらについては全て遺伝子レベルで決まっていることになってしまいます。
ゆえに、いくら飼育環境を工夫したとしても寿命に関しては覆すことは非常に難しいと言えます。
最後に
子どもたちは、いつも寿命を迎えたカブトムシ、クワガタに対し『ありがとう』と言って土に葬り手を合わせています。
飼育する際はしっかりお世話をすることを忘れず、『命を大切に!』と、いつも伝えてきました。
色んな学びがあり、奥が深いですね^ ^

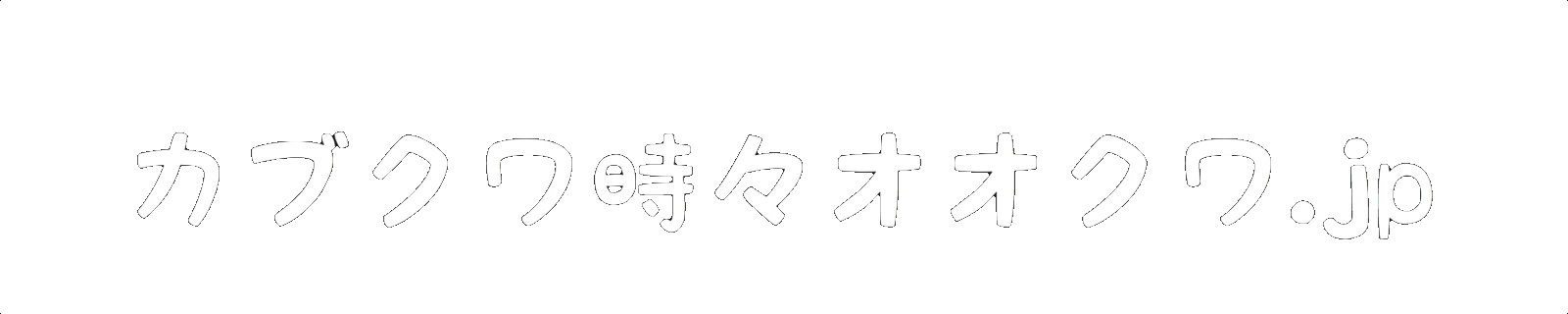

コメント